- なぜ肩こりが治らないのか?
- マッサージしてもすぐ戻るのはなぜ?
慢性的な肩こりの主な原因は、
首・肩周辺の血流障害による疲労物質の蓄積
そして
長時間の悪い姿勢(猫背・巻き肩・ストレートネック)による筋緊張です。
血流が低下すると筋肉に酸素が届きにくくなり、老廃物が溜まりやすくなります。
この状態が続くことで、
- 肩の重だるさ
- 首の張り
- 後頭部の痛み
- 緊張性頭痛(偏頭痛など)
といった症状につながります。
肩こりと姿勢の関係|猫背・巻き肩・ストレートネックが悪化させる理由
デスクワークやスマホ操作が多い方に多いのが
- 猫背姿勢
- 巻き肩
- 頭が前に出た姿勢
- ストレートネック
これらは首や肩の筋肉に常に負担をかけ、
⭕ 姿勢の崩れ=肩こりの原因
⭕ 肩こり=さらに姿勢が悪くなる
という悪循環を作ります。
慢性肩こりを改善するためには、
首と肩の位置を正す姿勢改善のためのリハビリ/施術が重要になります。
首の筋肉の解剖|肩こり・ストレートネックに関係する深層筋
首には多くの筋肉がありますが
肩こり改善に特に重要なのが
▶️板状(ばんじょう)筋(頸板状筋・頭板状筋)
▶️半棘(はんきょっ)筋(頸半棘筋・頭半棘筋・胸半棘筋)
です。
板状筋の働き|首こり・頭痛と関係する筋肉
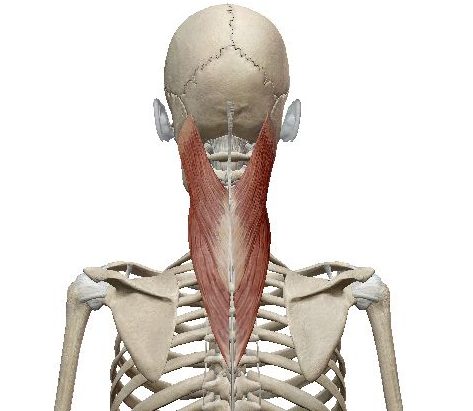
板状筋は
- 頭を上下に動かす
- 首を左右に倒す
- 顔を回す
といった動きで使われます。
長時間の前かがみ姿勢が続くと硬くなりやすく
首こり・後頭部の痛み・緊張性頭痛の原因になります。
半棘筋の働き|ストレートネックで硬くなる深層筋
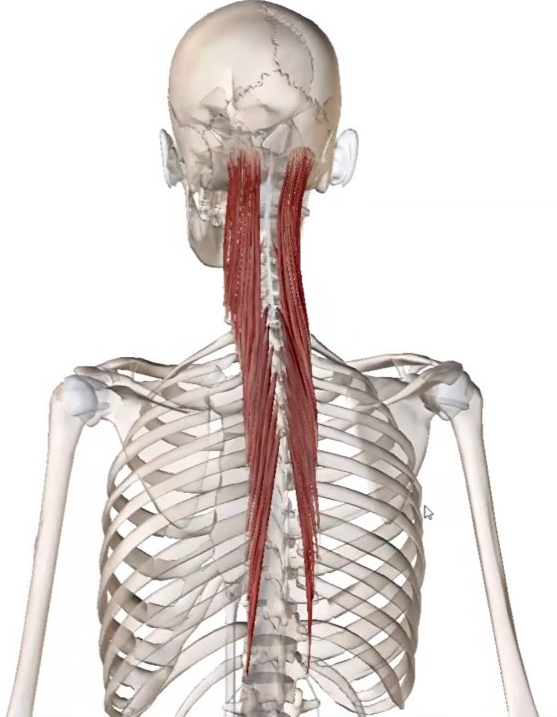
半棘筋は
- 顎を引いて姿勢を正す
- 体を左右に傾ける
といった動作に関わります。
ストレートネックでは常に引き伸ばされ
慢性的な首こり・肩こりの原因筋となります。
肩の筋肉の解剖|肩甲骨と関係する肩こりの原因筋
肩こり改善には肩甲骨の動きが重要です。
特に関与する筋肉は
- 肩甲挙筋
- 僧帽筋(上部・中部・下部)
- 菱形筋
です。
肩甲挙筋|肩をすくめると痛む肩こり筋
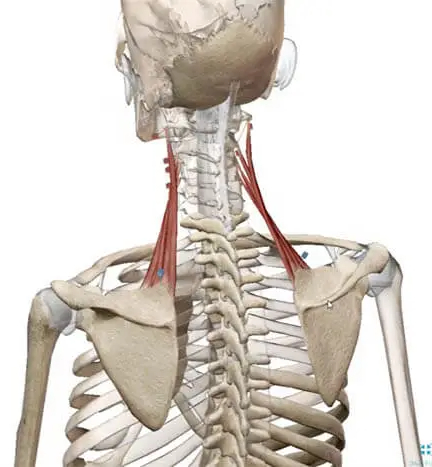
肩甲挙筋は
- 肩をすくめる
動きに関与します。
過緊張しやすく
💉トリガーポイント
💉ハイドロリリース
の対象になることも多い筋肉です。
僧帽筋|デスクワークでこりやすい筋肉
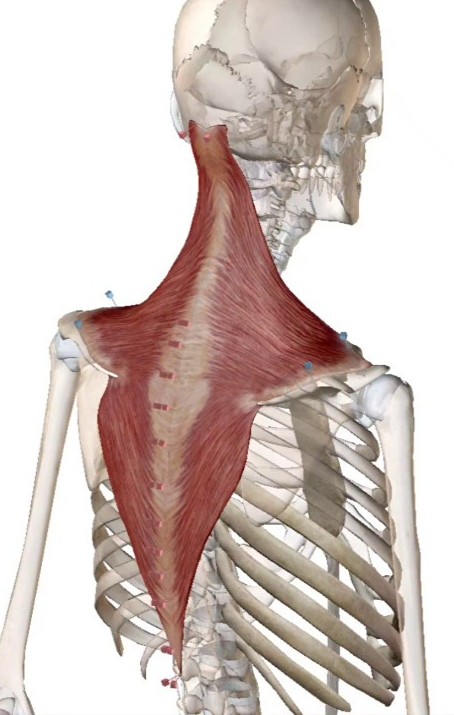
僧帽筋は三つに分かれます。
- 上部:肩をすくめる
- 中部:胸を張る
- 下部:肩甲骨を下げる
上部・中部は肩こりの主原因となりやすい部位です。
僧帽筋はひし形のような形をしており
▲上三角形の部分:上部
➖️真ん中:中部
▼下三角形の部分:下部
となってます。
菱形筋|猫背で弱くなる肩甲骨安定筋
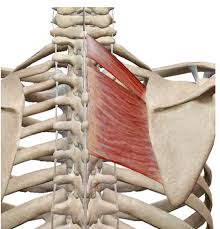
菱形筋には大菱形筋、小菱形筋の2筋から構成され
- 肩甲骨を背骨側へ引き寄せる(胸を張る)
働きを持ちます。
猫背姿勢では使われにくく筋力低下が起きやすいため
肩こりの再発予防にトレーニングが不可欠です。
慢性的な肩こりを改善するためのリハビリと筋力トレーニング
首・肩の筋肉を正しく使えるようになることが
慢性肩こり改善の鍵です。
当院では
▶️姿勢評価
▶️肩甲骨の動きの改善
▶️僧帽筋・菱形筋の筋力強化
▶️再発予防エクササイズ指導
をリハビリ技術に基づいて行っています。
マッサージで治らない肩こりでお悩みの方へ|整体とは違うリハビリ施術
- 長年肩こりが続いている
- マッサージしてもすぐ戻る
- デスクワークで首肩が限界
- 頭痛がする
このような方は
原因評価から行うリハビリ型施術がおすすめです。
整体とは異なる視点で
✔ 姿勢
✔ 首と肩の筋肉
✔ 肩甲骨の動き
を整え、根本改善を目指します。
ご興味のある方はぜひ一度ご相談ください。










お電話ありがとうございます、
肩・肘・手指専門リハビリ施術院でございます。